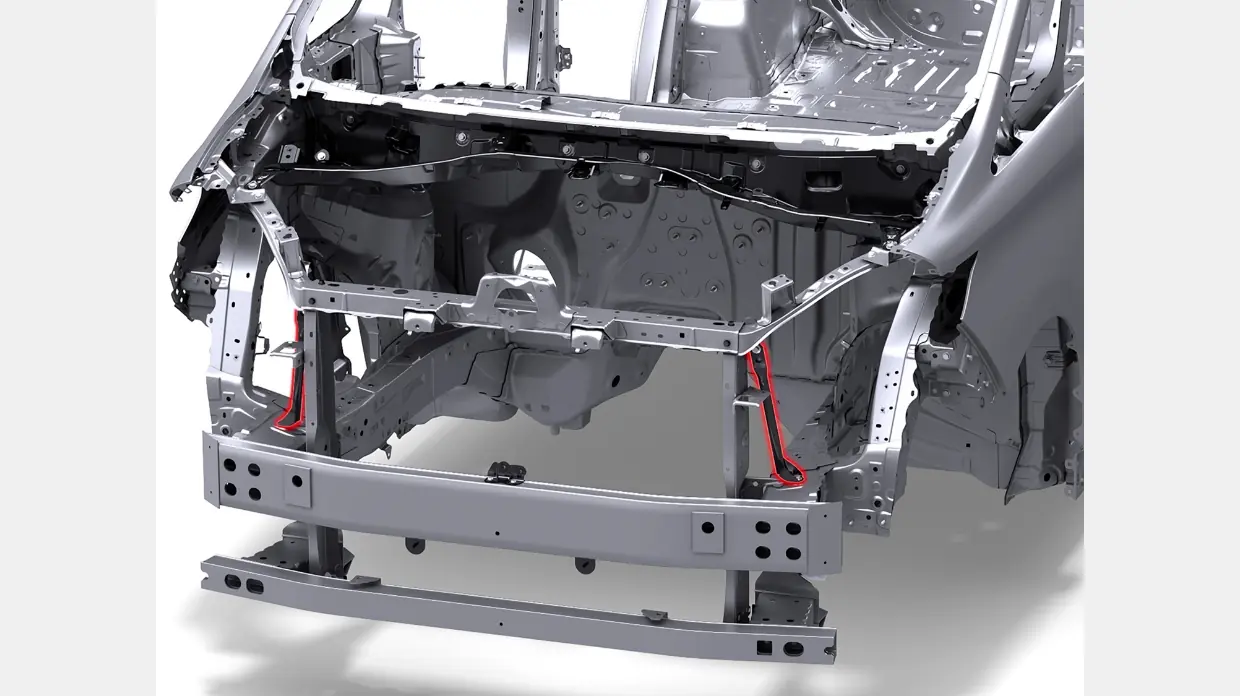名を馳せた職人や料理人は皆、挑戦者だ。前例のないことに挑み、ときに批判や不安を打ち払いながら、我が道を突き進む。彼らが得た栄光は、その道の先にしかあり得ないものなのだ。石川県の住宅街の一角にも、そんな栄光を手にした一軒の鮨屋がある。名は「すし処 めくみ」。食通なら知らぬ者がいないほど、名を轟かせる名店だ。道なき道を切り開くヴェルファイアの力強いトルクを感じながら、私は思いを馳せる。果たしてその職人は、どんな道を歩んだ末に現在の位置にたどり着いたのだろう、と。その偉大な足跡をたどるように、北へと走る。
食を求めて旅に出るフードツーリズムは、いまでは多くの人が知るところとなった。人がそこに求めるのは、現場に行ったからこそ味わえる独自性だろう。食材なのか、職人なのか、環境なのか、他の付加価値なのか。訪れねば味わえない特別な体験を求め、旅人は長い道をたどる。
そんなフードツーリズムを語るとき、必ず名が挙がる店がある。「すし処 めくみ」。金沢の中心部から車で30分ほど離れた住宅街に佇む、小さな鮨屋だ。この店が、なぜこれほど人を惹きつけるのだろう。その答えを探すために、北陸へと向かった。
予約は夜だったが、金沢に到着したのはまだ日も高い時間だった。だが問題はない。自然と文化が融合したこの古都には、走りたい道が無数にある。
私は心の向くままにヴェルファイアを走らせる。海沿いの道路から見渡す群青色の日本海。2.4L直列4気筒ターボエンジンの伸びのある走りが、ドライブの爽快感をも加速させる。山道を駆け抜けた先から見下ろした町並みは、この金沢が戦火を免れ城下町の区画をそのまま遺していることを如実に伝えた。風情あるにし茶屋街を通り抜けるときは、レスポンスの良いエンジンがまるで体の一部のように感じられた。
予約の時間が近づいている。金沢のドライブを存分に楽しんだ私は、その高揚感のままに店へと向かった。
Other Photos
出迎えてくれた店主・山口尚亨氏の第一印象は、“物静かだが芯の強い人物”だった。黙っていても物事の本質を見抜くような、静かな迫力が感じられたのだ。少し時間を過ごすと、その第一印象は半分覆り、半分は確信に変わった。
山口氏は饒舌だった。
食事の間、常に話し続けている。一を問うと十の返答がある。だがその言葉はきっと、何を話そうか考えた末のものではない。それは彼の心から、まるで汗や涙のように自然に溢れ出てくるものに思えた。饒舌に語られる言葉そのものが、山口氏の情熱の結晶なのだ。
たとえばシャリについて。
「365日、毎日炊いていますが、一度として同じものはできない。炊けば炊くほど違いが見えてくる。繰り返すごとに“自分がまだわかっていない”ということが、わかるんです」
山口氏のシャリは、口に含んだ瞬間に自動的に四方に拡散されるような見事なシャリだ。それでも毎日が研鑽と研究の連続なのだという。
魚に関しても同様だ。朝4時起きは当たり前。時期によっては1時、2時に起きることも、まったく寝ないこともある。車に乗ってまず市場まで片道100km。それでも足りず、能登半島中を魚を求めて駆け回る。数年前までは年間走行距離8万km。ここ2年ほどは漁師が山口さんの求める仕事を覚えてくれたため、その走行距離はだいぶ減ったというが、それでも年間3万5000kmは走る。まだ見ぬ理想を求め、海沿いを、山道を、里山を、まるで切り開くように走り続ける。
「本当に良いと思えるものなら、価格はどうでも良いんです。価格ではなく、味だけで判断したい。ただその確信を得るためには、どうしても自分の目で確かめたい」
それは執念とも呼ぶべき、鬼気迫るような情熱だ。
1972年、石川県で生まれた山口氏は、銀座の老舗で職人のキャリアをスタートする。しかし東京の店が肌に合わず、数軒を渡り歩いた後の2002年に故郷である金沢に「すし処 めくみ」を開いた。
最初の数年は客が入らなかったというが「なぜここでやるのか」を突き詰めるうちに地元の魚に魅せられ、店も徐々に人気を集めた。
「江戸の魚でつくるから江戸前鮨。だから、この場所では江戸前鮨はできないと思っていました。しかし続けるうちに、“江戸前”の根っこにある米や技術の出し方、さらに根本にある江戸前の魂までも深く理解できるようになりました。いまでは世界中どこへ行っても江戸前鮨ができます」
それでもこの地でやる意味を見失ってはいない。魚や米はもちろん、店がまとう空気や香りでも、この地独特のものを表現する。それは教科書にない手探りの挑戦だったことだろう。そしてその挑戦を支えたのは、山口氏の熱意に他ならない。
「若い時よりも情熱は上がっています。それを心の奥に仕舞う技術が上達しただけ」
つまみから始まったコースが握りになり、甘海老、鰤を経て蒸したいくらが出てくる頃、話題は山口氏の仕事観へと移った。
「感覚だけでは駄目なんです。感覚だけに頼っていると、環境の変化についていけない。だから科学的な分析も必要なんです」
たしかに山口氏の話には「アミノ酸と脂肪酸による熟成の違い」「天日米に含まれるアミロース成分」といった学術的な話が差し込まれる。だが理論に偏っているかといえばそうではない。
「喧嘩しながらやって来た二人がいたら、帰るまでに仲直りさせたい。そういう思いやりは、料理にも出てくるものだと思うんです」
理論があり、思いがあり、情熱がある。山口氏の言葉は、いつまでも聞いていたくなるような熱量に満ちていた。
もちろん客を喜ばせたいというサービス精神は一番にあるのだろう。しかし、このストイックな向上心は、それだけでは説明しきれないような気がした。自分自身を欺かず、ただ自らの心に問いかける。きっと彼は、たとえ客が満足しても自分が納得できなければ、それを良しとはしないだろう。誤解を恐れずにいうならば、それは究極の我儘だ。
「ものづくりとは結局、自分づくりなんです。自分をどうしていくか。それを考えていれば自然と、つくったものに個性が出てくる」
そんな言葉が心に残った。
満足の末に店を後にする。
山口氏と奥様は、走り去る私を店の前でいつまでも見送ってくれた。バックミラーの中で小さくなっていく二人の姿を見ながら、私は今日の時間を振り返る。おいしい鮨と豊かな時間があった。だがそれだけではない。「すし処 めくみ」に教えられたのは常に学び、挑戦を続けることの尊さ。働くこと、生きること、自らの道を突き進むことの意味。挑戦を形にしたような車、ヴェルファイアのハンドルが、相棒のように頼もしく思えた。
Other Photos