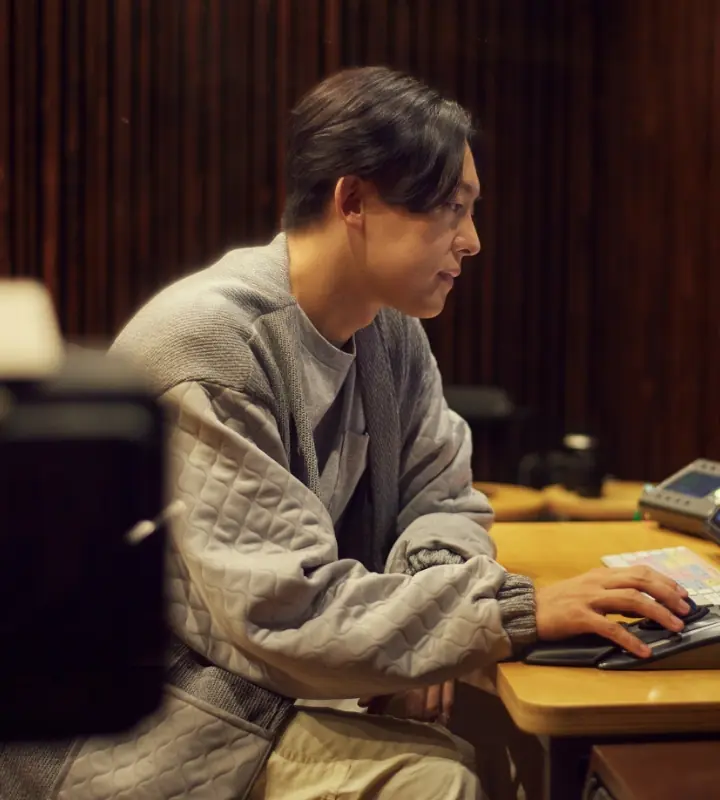約400年前に日本に伝来し「伊万里」の名で世界に愛された日本の器「有田焼」。日用品としても広く普及した日本で最も長い歴史を持つこの美しい磁器は、戦後、時代に取り残され、産業は衰退の道を辿っていった。それを再び世界が求めるラグジュアリーな器へと生まれ変わらせた人物が「アリタポーセリンラボ」の松本哲氏だ。創業220周年の節目の年を経て、さらなる飛躍の未来を描く松本氏の元に、ラグジュアリーカーのかつてない世界を切り拓いたアルファードがやってきた。
創業1804年。2024年に220周年の節目を祝うとともに、次の10年に向けた価値創造へと歩みだしている「アリタポーセリンラボ」の代表・松本哲氏。またの名を松本弥左ヱ門。「弥左ヱ門窯」という有田焼の窯元を興した初代から数えて7代目にあたる。
一族が運営する会社は、昭和40年代、5代目の頃に一族経営としては地域最大規模の有田焼業者へと成長した。しかし2000年代初頭、有田焼全体の需要低下による市場の縮小で苦戦を強いられ、押し寄せる価格競争の波は同社の存続を不可能にするほどに苛烈なものとなった。この先の見えない時代に、同社を引き継いだのが松本哲氏だ。
「当時の有田焼の弱点は、もはや同時代の住環境にはデザイン的に合っていないこと。製造業者の利益が少ない商習慣にとらわれて身動きがとれないことでした」
松本氏はこの2つの課題を乗り越えらえなければ自社の存続のみならず有田焼全体も危ういと考えた。思索の末にたどり着いたのが自社内に「アリタポーセリンラボ」というブランドを立ち上げるという計画だった。
「まずアリタポーセリンラボを少量生産のラグジュアリーブランドと位置づけました。そして、伝統的な有田焼の技術、デザインを使いながらも、パターンを変えたり、色を変えたりすることで見た目を現代の居住空間に合わせたのです」
松本氏が最初に考案したのは、光沢感のある白地に、図柄を描き、赤・青・金といった伝統的な色がつけられる一般的な有田焼に対して、図柄はそのまま、しかし白地はマットに仕上げ、色はモノトーンにするというもの。代表作はプラチナあるいはゴールドを使ったもの。
Other Photos
このかつてない有田焼は海外の展示会への出展を機に、東京、パリ、ニューヨークといった大都市に店を構える百貨店バイヤーに注目された。注文は次々に舞い込み、松本氏は色やデザインのバリエーションを増やしていった。ほどなくして、器が評価に大きく影響するミシュランガイドの星付き店など、一流レストランでも使われるようになり……
「料理店だけでなく、有名な香水ブランドやお菓子ブランドなどともコラボレーションの話をいただくようになって、アリタポーセリンラボのほうが当時の社名よりも有名になったのでブランド名でなく社名にしたんです」
革新による有田焼の復活。しかし、この成果に満足して、松本氏が歩みを止めることはなかった。今、松本氏は変革の先を追い求めている。その象徴として発表されたのが、実質的にはそれぞれ1点物のアートピースシリーズ「七代松本弥左ヱ門 ゴールドイマリ “モノリス”」。この作品からはアリタポーセリンラボというブランドをより強固なものとしようとする松本氏の強い意思が感じられる。
なぜなら、七福神をイメージして生成AIが出力した形をベースにデザインしたという独特の複雑な形状に、コミカルにアレンジされた伝統の文様が大胆な色使いで描かれているこの作品群を実現しているのは、受け継がれた有田焼のデザインテーマと松本氏によるアレンジ、そして、磨き上げられた職人技術でしかないからだ。これまで、アーティストとのコラボレーションによって大英博物館永久所蔵作品を生み出すこともしているアリタポーセリンラボだが、今回はアリタポーセリンラボ単独の純粋な作品。それはブランドそのものが持つインテンシティ(強度)の表現と考えられないだろうか。
奇しくも、松本氏の最初の挑戦と同じ頃、ラグジュアリーカーの分野で世界にそれまで存在していなかったカテゴリを切り拓いたのがアルファード。現在すでに4世代を数え、歩みを止めることなく挑戦を続けていることを、今回、有田の町を訪れた最新のPHEVモデルに触れて松本氏は確認した。
「私はクルマはそんなに詳しくないですけれど、もちろんアルファードは知っていますよ。ブランドですよね。もう4世代目なんですね」
普段、自分では運転しない上に、車酔いもしやすいという松本さんにとって、後席の居心地は重要。果たして、PHEVのアルファードはお眼鏡にかなうのだろうか?
「まだ少ししか乗っていませんが、これまでよりもさらに静かで、乗り心地が良くて、優雅な移動ができそうですね」
PHEVのアルファードは約73km*のEV走行可能距離を誇り、日常移動の多くをモーター駆動で走行可能。長距離移動時などエンジンが動作する際もHEVモデルとの比較でもエンジン回転数は約800rpm(60km/h時)低く、車内騒音は同条件で1/3程度低減した。バッテリーと燃料タンクがフロア下に配置されていることから重心高もHEV比でさらに低くなり、それに合わせて足回りのセッティングが最適化されたことから、乗り心地に直結する加減速、回頭時の姿勢の変化が少ない。
その後しばらくして「これはファーストクラスですね」と微笑む。
「僕は体が大きいけれど車内にはたっぷりと余裕があるし、ルーフの開け閉めや照明・空調などの操作を、すべて手元のタブレットで完結できるのもいいなと思いました」
有田焼のラグジュアリーブランドとミニバンのラグジュアリーブランドの邂逅。松本氏にとって、そもそもラグジュアリーとはどういうものかをたずねてみると……
「ラグジュアリーと言われると、華美で派手なもの、というイメージを持つ方もいらっしゃるのではないかと思います。でも私は、ラグジュアリーなものは居心地が良い空間を作り、生活の質を上げてくれるものだと考えています。アリタポーセリンラボは器でそれを目指しているけれど、アルファードはクルマでそれを目指しているのかもしれませんね」
PHEV化も、優秀なショーファー(運転手)が運転しているかのような「快適な移動の幸せ」というアルファードの本質をさらに高めている、という説明を受けると。
「なるほど。私は7代目ですが、何代も続くものって、続くべき理由があるはずです。その理由、つまり自分の価値を自分がきちんと理解して、時代に合わせながら再現し続けられることがブランドだと私は考えています。アルファードは快適な移動を追い求める、というところでブレることがないのであれば、その分野の自動車のトップブランドとして、100年、200年、あるいは400年と歴史を紡いでゆくのではないでしょうか?」
松本さんの目には、自身とアルファードが走って行く道がすでに映っているかのようだった。
*EV走行距離[充電電力使用時走行距離](国土交通省審査値)
■充電電力使用時走行距離は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じてEV走行距離は大きく異なります。
■エンジン、駆動用電池の状態、エアコンの使用状況や運転方法(所定の速度を超える)などによっては、バッテリー残量に関わらずEV走行が解除され、エンジンが作動します。