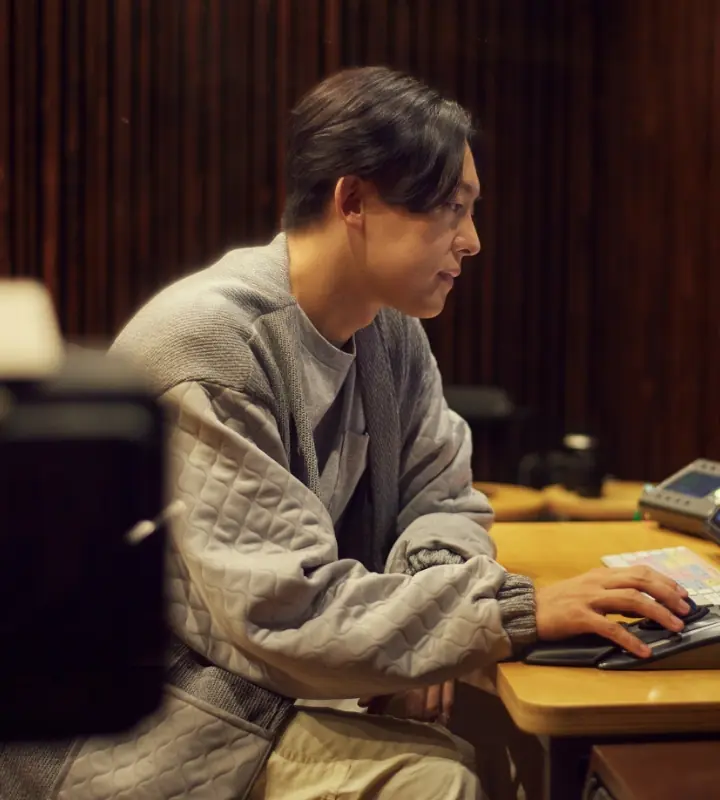日本の醤油は鎌倉時代に中国から伝来し現在の和歌山県湯浅町において、今も「金山寺味噌」として伝わる味噌から生まれたという。以来、醤油の町として賑わった湯浅。しかし、21世紀初頭、この歴史は忘れられ、湯浅の町に醤油蔵は数えるばかりしか残っていなかった。この湯浅で「世界一の醤油」を生み出し、ガストロノミー界から注目を集めているのが「湯浅醤油」。その代表にして醤油の醸造家である新古敏朗氏は奇しくも長年ヴェルファイアを愛するオーナーだった。新古氏はなぜヴェルファイアを相棒に選ぶのか? そして彼の目に最新のヴェルファイアPHEVはどう映るのか?
2023年3月、フランスの公営テレビ局がワインの聖地・ボルドーはサント=テール地区にてオーガニック醤油が造られていることを報じた。地元のワイナリー「シャトー・クーテット」がフランスの原料を用いてワイン樽で醸造・熟成した醤油。こんな前代未聞の醤油をフランス伝統のワインの造り手とともに、同地区に土地を購入して生み出したのが、醤油発祥の地・和歌山県湯浅町にある「湯浅醤油」の代表・新古敏朗氏だ。
2024年に完成した醤油は「SHINKO」と名付けられ、NOIRE(黒・こいくち醤油)とBLANCHE(白醤油)の2種類がある。主にフランスで流通し、初回生産分はたった3カ月で売り切れた。普段はワインを仕入れている飲食店、特にミシュランの星を獲得するような高級料理店からの引き合いは予想以上だったという。小売価格は日本で販売されたNOIREの場合、200mlで1万円という醤油の常識では考えられない高価格だ。
「昔からなんの裏付けもなく、美食が集う世界の大都市・パリ、ロンドン、ニューヨークには進出したいって会う人会う人に言っていました。ほとんどの人は「夢が大きくていいですねぇ」としか言いませんが、夢って口に出さないと実現しない。でも、言えばきっと現実になる」
フランスで初の醤油完成の報を受けて、アメリカからも声がかかった。続いて、アフリカ、スペイン、歴史をたどれば醤油の祖国ともいえる中国からも醤油造りオファーが来ているという。
新古氏は湯浅町伝統の味噌「金山寺味噌」を醸す蔵「丸新本家」の5代目・嫡男として生まれた。生家は現在は「伝統的建造物群保存地区」となっている、味噌・醤油蔵、麹屋がかつては何軒もあった街区のすぐそばにある。しかしこの地と醤油の歴史を新古氏は成人するまで知らなかったという。
「大阪のお客さまから湯浅なのに醤油はないんか? とあんまり言われるので調べたら、湯浅は醤油発祥の地だった。確かに醤油蔵があるな、湯浅醤油という言葉はあるな、とは思っていましたが、僕は湯浅に生まれ育っているのに、ここが醤油発祥の地だなんて大事なこと、誰からも聞かなかった」
新古氏はその無関心に愕然としたという。中国に起源を持つ金山寺味噌が湯浅に伝わったのは13世紀。そこから醤油の原型が生まれた歴史は、単に調味料の伝来と発祥にとどまらない奥深い人間の物語だった。新古氏は醤油に魅了されてゆく。
「その頃、地元に残っていた醤油を造る家はわずか5軒ほどです。でも以前はたくさんの醤油蔵が湯浅にあった。僕は、こんな大事なものを地元の人が忘れて、伝統がなくなるのは、違うと思うんです」
2002年、意を決して自社の敷地内に醤油蔵を作り上げる。湯浅の伝統を背負い、世界に打って出る覚悟を込めて、大胆にも社名は「湯浅醤油 有限会社」とした。そして、1500年前の農業書を参考にしながら、発祥の地・湯浅の名に恥じない「世界一の醤油」を生み出そうと試行錯誤を続け、JAS規格最上位の「特級」と比べても約1.5倍という、前代未聞の旨味を持つ醤油が完成する。
Other Photos
やがて世界が注目することになる道のりの始まりだった。その後も新古氏は湯浅醤油で様々な新しい醤油を造り続けた。日常的な醤油、伝統的な醤油、料理に合わせた個性的な醤油、素材も醸造も特別に作り込んだ醤油……今やそのラインナップはワイナリーのように幅広い。
「「和食」は世界の人々に広く愛されるようになりました。その味の決め手となる醤油は、もはや「日本のローカルな調味料のひとつ」ではありません。醤油を使う人々の味覚も国籍も、料理の種類も広がる中、“昔ながらの味”だけにこだわっていたのでは、その時代を生きる人たちに驚きと感動を与えられない。どんなときも「これぞ世界一!」と感じてもらえる醤油を造り続けること。これが使命です」
醤油という日本人ならば誰もが知るコモディティ中のコモディティに、これほどに豊かな可能性があることを、おそらくほとんどの人は気付きもしなかっただろう。新古氏はそのコモディティの手を力強くつかみ、世界の頂点まで連れてゆく。
「みんなが右に行くなら僕は左に行く。そこには誰もいないから」
そんな人物がヴェルファイアを愛しているのは、自然なことに感じられてならない。なぜなら、ヴェルファイアは、西洋の自動車文化ではラグジュアリーの文脈に入らなかった車型をラグジュアリーカーとして成立させ、強い個性を発揮しているクルマだからだ。
孤高の醸造家にヴェルファイアを相棒に選ぶ理由をたずねるとこう言う。
「僕はそもそもスポーツカーに乗っていたんです。だからクルマが好きで運転は苦にならないどころか楽しいんですが、今は一人で運転を楽しむだけでなく、お客さまも多いし、人や物を余裕をもって運べる必要もあります。そんなわがままを叶えてくれるクルマを探してたどり着いたのがヴェルファイアです。200kmでも300kmでもヴェルファイアを運転して移動しますよ。高速道路をのんびり走っている時間は、僕にとっては数少ないゆっくりと考え事をする時間でもあるんです」
PHEVモデルとなったヴェルファイアがやってきて、湯浅醤油の広い敷地で短時間の試乗をすると「欲しい!」
長距離移動をHEVモデル以上に高効率化する機関、思索と運転の時間をさらに上質にするモーターの作動範囲が広いことからくる静粛性、HEVモデル以上に大きなシステム最高出力(HEVモデル最高184kWに対して225kW*.Excecutive Lounge・E-Fourの場合)が実現する初期トルクの厚みとより高い加速性能、そして、大容量バッテリーと燃料タンクをフロア下に配置したことによる低重心化とそれに合わせた足回りのセッティングが実現する姿勢の安定性と運転の楽しさをすぐに感じ取ったのだ。
Other Photos
「僕のことを変なヤツだって言う人もたくさんいるけれど、100人いたら1人くらいは、いいですね! 一緒にやりましょう! って言う人がいる。変わり者の僕と引き合う人がいる。そういう人と一緒に挑戦を重ねてきて今の僕がある」
新古氏はそんな自分のことを「磁石」に例える。
「合う人とは自然とひっつくし、合わない人とはひっつかないって磁石みたいでしょう? ヴェルファイアも、僕とひっついているんでしょうね」
撮影のためにちょっとシリアスな表情をお願いしても、ヴェルファイアに触っているとついつい笑みが漏れてしまう。新しいヴェルファイアは、新古氏の新しい相棒にふさわしい存在だったようだ。